南部裂織

八戸市中心街にある老舗百貨店三春屋で、「南部裂織展」を見てきました。
(※主催者の許可を得て写真の撮影・掲載をしています)

その土地に住んだら、その土地のことを知った方がより生活が豊かになる。
子供の頃はあまり興味が無かったのですが、千葉に住み、全国いろいろな場所に行ってみると、その土地に根ざしたものがとても面白く思えるようになりました。
私が住む青森県八戸市には、刺し子である南部菱刺しのほかに、南部裂織があります。
この展示会は、伝統工芸士である井上澄子さん主宰の工房「澄」choのメンバー10人の作品を展示・販売しています。
 展示を見た後で「裂織の本」を読み、少し裂織のことを学びました。
展示を見た後で「裂織の本」を読み、少し裂織のことを学びました。
それによると、この地方の裂織の歴史は比較的新しいことを知りました。
裂織で横糸として使う古布の素材である木綿が普及したのが明治中頃、東北本線開通の時。
それまで麻の地味な色合いの素材しかなかったため、鉄道により色彩豊かな木綿がもたらされたので、裂織も極彩色のものになったのだそう。
また、囲炉裏からこたつに変わる時期だったため、仕事着よりも、こたつ掛けのようなインテリア用品として仕立てたのも特徴のひとつだとか。
てっきりこの地方のものは地味だと思っていたので、意外でした。
歴史を知ると、面白いですね。
(ちなみに、青森県西部の津軽地方では裂織のことを「さくり」と呼ぶそうです。
現代の「さくり」には、こういったものも。)

会場では織り機があって体験も出来、実際織ってみてわかることもあるからと、勧められるままに体験してみました。

やってみると、これが結構楽しい。
かなり真剣に、15センチくらい織ったんですよ。
でも、やってみると意外にうまくいかないんです。
古布をちゃんと詰めていかないと隙間ができるし、上糸と下糸を間違えるとだめだし、左右の端も、古布を引っ張りすぎると横幅が変わってしまうし。
でも、一番感じたのが模様というか、色調というか。
古布を使うことと、その布も織る時に詰めるので、織ってみないとどのような色調や模様になっているかが分からないんです。
きっと上達すれば、ある程度意図したものに仕上がるのかもしれませんが、でもその不自由さがなんかくやしい。
僕は、今の若い人も、こういう伝統産業で自分にあった良いものがあれば、欲しいと思う人はたくさんいると思うんです。
リサイクルや古いものを大切にすることも必要だと分かってますから。
でも、そうは言っても豊かな時代に生まれているので、こういうものでもおしゃれなものの方が良い。
わがままかもしれないけれど、でもそっちの方が良い。
そう思うと、やはり模様や色調をコントロールできた方が良いのではないか、でも実際やってみると意外に難しい。
難しいけど面白い。
でも、なんだか、はまりそうです。
師範の手さばきは、とても早かったです。



絵や模様も表現できるのだそう。
左の作品の絵の部分、こんな感じです。




色調がとても美しいと思いました。

右の作品の模様がきれいです。

中東チックな色調です。

使う古布で全然違うんですよね。

会場で見た中で、個人的に好きな色合い。
渋線です。
ボタンなどの小物が、もう少し良いのが選べたら・・・でも、探すのが大変なんですよね。
そういうのって、プロデュースする人がいれば良いのでしょうか。

裂織は究極のリサイクル。
裂織の製品の活用法や、若い人が欲しくなるような製品の型、小物、色調などを、もっと考えると、さらに可能性が広がるように思いました。
この裂織、布ぞうりと似たような概念なのかもしれません。
ですから、もしかしたら布ぞうりの製作体験がありますが、そのように、裂織の製作体験で楽しさを共有する、という楽しみ方もあるのかもしれません。

コメント2件
なんとまぁ、そうだったんですね!?

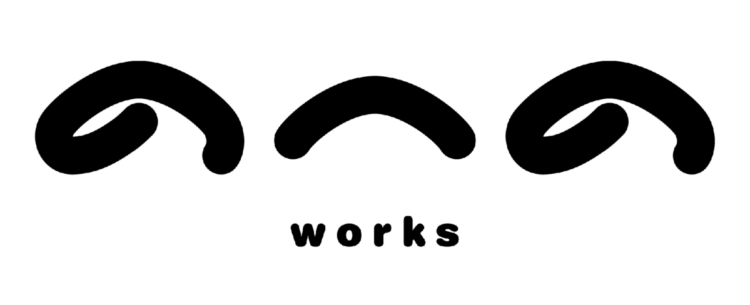
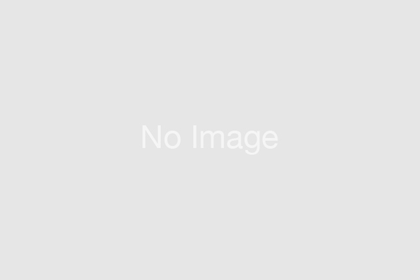





このハガキのデザインは私だ^^