2010-02-25
お庭えんぶり

先日、八戸の民俗芸能であるえんぶりを見てきました。
えんぶりは、その年の豊作祈願をするお祭り。
歴史は古く、鎌倉時代と言われているよう。
八戸市を中心に近隣市町村合わせ現在は40のえんぶり組があり、うち今年の八戸の祭事としてのえんぶりには、33組が参加。
毎年2月17日の朝7時に長者山新羅神社での奉納摺りを皮切りに、20日まで開催されています。


僕が見たのは、更上閣という明治期に建てられた財閥の邸宅だったところで行われる「お庭えんぶり」。
最終日で、出演は山道と石堂。












このお祭りは、深いです。
烏帽子をかぶった太夫の踊りの形で、「ながえんぶり」と「どうさいえんぶり」があり、太夫の舞いの合間に行われる子ども達による踊りにも、エンコエンコとか恵比寿舞い、大黒舞いとかあるんですが、組によってその組にしか無い踊りやら、ここの組はこれが違うとかがあるよう。(だんだんわかってきました)
そして、お囃子も踊りで違うほか、そのリズムもまた良い。
さらに、歴史が古いからか、えんぶり組のマークや太夫が羽織っているものの図柄もまたモダン。
その奥深さが現在は全然ちゃんと伝えられておらず、とてももったいないと思っています。
あまり専門的にならず、軽く、でも面白さを、いつか何かのかたちで伝えてみたらな、と思っています。
関連記事

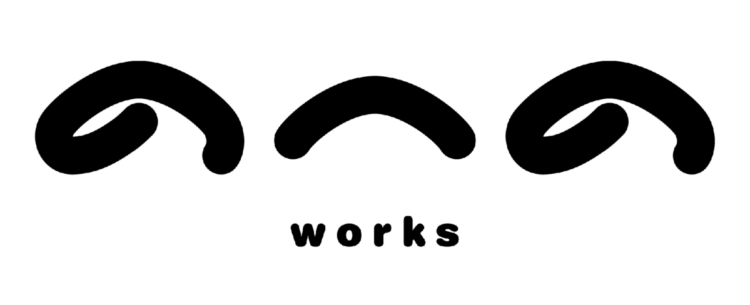
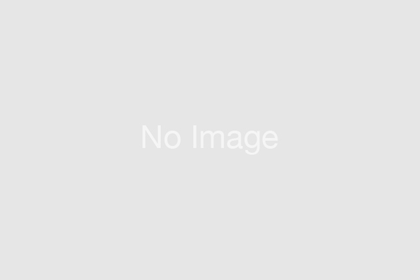





コメントを残す